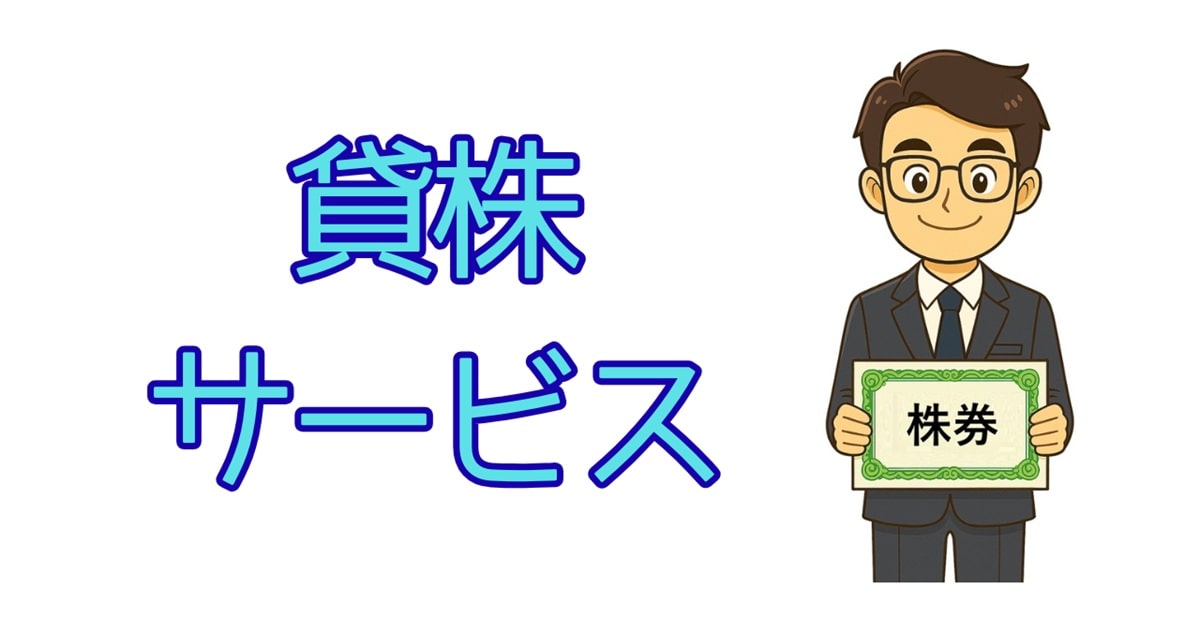こんにちは、おくりんです。
株式投資をしていると、「貸株サービス」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。貸株サービスは、保有している株を貸し出すだけで貸株金利を受け取ることができるサービスで、一見お得なことばかりに見えます。
しかし、貸株サービスは、使い方を間違えると損をするリスクもあるのです。
おくりんは貸株サービスの存在を知ったとき、これはお得なサービスだと思って持ち株のすべてを貸株サービスにしていました。
しかしよく調べると、もらえる金利が少ないわりにデメリットが大きいとわかりました。
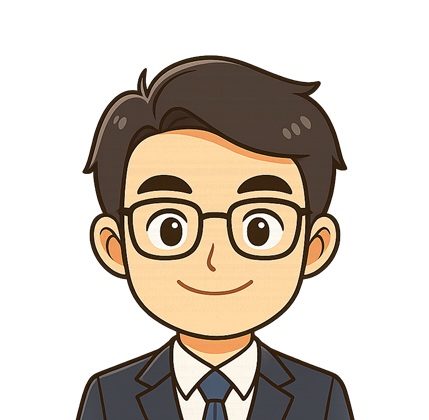
今は貸株サービスは全く利用していません。
なぜそうしたのか、この記事で詳しく説明します。
この記事では、貸株サービスの仕組みからメリット・デメリット、そして利用する場合の注意点を初心者向けにわかりやすく解説していきます。
貸株サービスとは?
貸株サービスとは、あなたが保有している株式を証券会社に一時的に貸し出すことで、貸株金利(いわばレンタル料)を受け取る仕組みです。
証券会社はその株を空売りしたい他の投資家に貸し出し、その対価として得た利益の一部を、貸株を提供したあなたに還元してくれるという仕組みです。

参考リンク
貸株サービスのメリット
貸株金利で副収入が得られる
保有しているだけの株から金利収入が得られます。銘柄によって貸株金利は差がついており、年利0.1%〜10%超の場合もあります。
たとえば、貸株金利が1%の株を200万円分貸し出せば、年間で2万円の金利収入が得られます。
金利は週単位で見直されることが多く、市場の需給に応じて変動します。
株はいつでも売却可能
「貸してしまったら売れないんじゃ?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。貸株中でも通常の売却注文が可能で、流動性を損なうことはありません。
対象銘柄が幅広い
東証に上場している株のほとんどが対象です。ETFやREITも一部対応しています。
優待・配当も受け取れる
条件付きですが、優待・配当も受け取ることができます。
「株を貸したら優待や配当がもらえなくなるのでは?」と心配される方も安心してください。
証券会社の貸株サービスのところで、株主優待・配当金自動返却設定をすれば、権利確定日のみ自動的に株が返却され、優待や配当もきちんと受け取れます。
貸株サービスのデメリット
株主権利が制限される
貸株中は、株主名義が証券会社に変更されるため、以下の権利が制限されます。
- 株主優待が受け取れない(自動返却設定で回避可)
- 配当金が「配当金相当額」として支払われ、名目上は配当ではなくなる
- 株主総会での議決権を行使できない
税制上のデメリットがある
これが意外と見落とされがちなポイントです。
- 貸株金利や配当金相当額は「雑所得」として課税される
- 配当控除が使えない
- 株式売買の損失と貸株金利の利益は損益通算できない
- 年20万円を超えると給与所得者でも確定申告が必要
つまり、貸株金利をもらっても、それが課税対象になって貸株金利以上に手取りが減る可能性もあるのです。

このデメリットを知ったため、貸株サービスをやめました。
証券会社が破綻した場合のリスク
貸株している株式は、証券会社の破綻時に保護されません。
- 分別保管の対象外
- 投資者保護基金の適用外
- 株が戻ってこない可能性がある(一般債権者扱い)
つまり、証券会社が倒産した場合に最もリスクが高い資産のひとつになります。
長期保有優待が受けられない可能性も
一部の企業では、「1年以上保有」などの継続保有条件付き優待がありますが、貸株中は「保有していない」とみなされる場合があります。
この場合、優待がもらえなくなる可能性があるため、長期優待狙いの銘柄では要注意です。

このデメリットも嫌ですね。私は優待株も好きなので。
貸株サービスの効果的な使い方
こんな場合に貸株サービスはおすすめです。
- 長期保有予定の高配当株(売る予定がない)
- 優待に興味がない成長株
- インデックス投資(ETF)で長期保有している資産
こんな場合だと貸株サービスは避けるべきです。
- 短期売買を頻繁に行う人(設定管理が面倒になります)
- 株主優待を狙っている銘柄
- 所得が多く、総合課税の税率が高い人
まとめ
貸株サービスは、ただ保有しているだけの株式を収益化できる有力な手段で、使い方次第で武器になります。
特に、長期投資家や高配当銘柄を持っている人にとっては、ほぼ放置で年利収入が得られるという魅力的な仕組みです。
ただし、税金・権利・破綻リスクという見落としがちな落とし穴もあるため、しっかりとルールを理解して使うことが重要です。
この記事のポイント
- 貸株サービスは株を貸して金利を得る仕組み
- 配当や優待の自動返却設定が可能
- 税金面では「雑所得」扱いになるため注意
- 長期保有+優待なし銘柄におすすめ