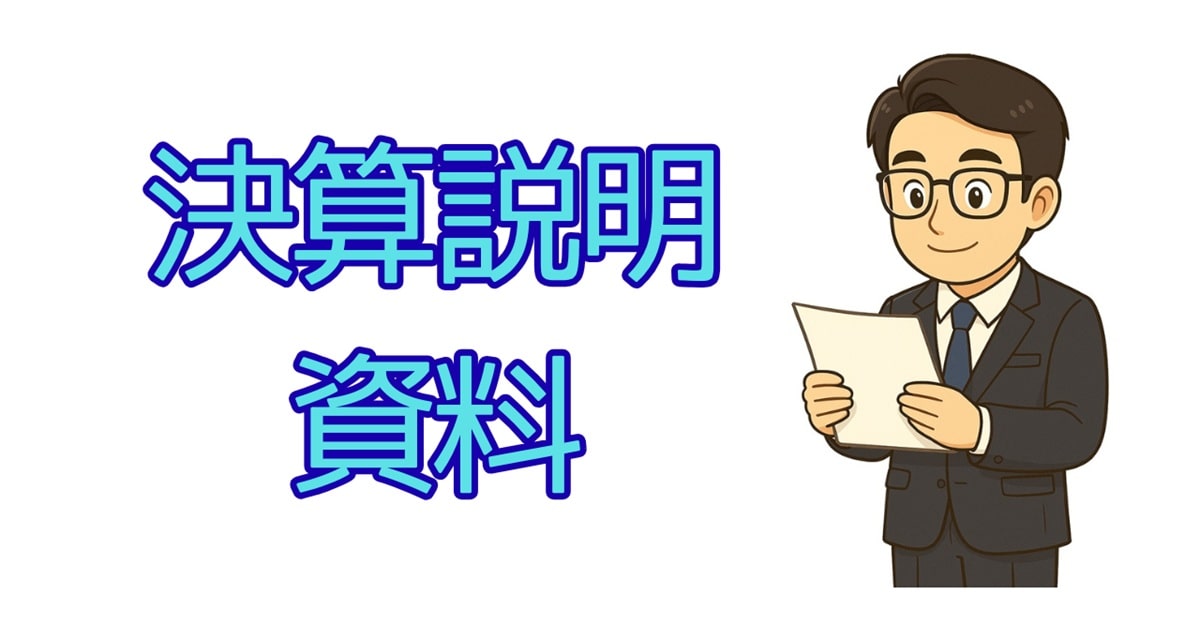こんにちは、おくりんです。
株式投資において、「この企業は将来伸びるかどうか?」を判断する材料のひとつが決算説明資料です。私は株を買う前に、今後2〜3年でどのくらいの利益が得られるかを仮定し、その根拠として決算説明資料を活用しています。
今回は、その決算説明資料から業績を予想する際の注意点と分析のコツを、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
決算説明資料とは?
決算説明資料は、企業が四半期決算時に合わせて公表するIR資料のひとつです。決算短信が主に過去の業績を定型フォーマットで示すのに対し、決算説明資料では今後の成長戦略や事業ビジョンが語られます。
たとえば:
- 「今後3年間で売上高を2倍に」
- 「5年以内に海外展開で500億円規模の事業を目指す」
といった企業の成長戦略が語られているのが特徴です。
決算説明資料を読む際の7つの注意点
会社の「見通し」はあくまで仮説である
企業が語る将来像は、希望的観測を含むこともあることに注意が必要です。すべてを鵜呑みにせず、実績とのギャップを検証することが重要です。
過去の資料と一貫性があるか?
2〜3年前の資料と現在の内容を比べて
- 当時の目標は達成されたかどうか
- 成長戦略の修正が繰り返されていないか
など、一貫性と信頼性をチェックしましょう。
2〜3年前に掲げていた目標が現在達成されていなかったり、目標が毎年コロコロと変わっているような企業は、信頼性が低いと判断できます。
数値だけでなくストーリーを見る
なぜその戦略を取るのか?競争優位性は?など、戦略のロジックや説得力に注目しましょう。
見落としがちですが、質疑応答セクションは重要です。決算説明会の質疑応答では、資料に記載されていない重要な情報が得られることが多く、経営陣の本音や詳細な戦略が明らかになる場合があります。
IR資料の「盛りすぎ」に注意
また、決算説明資料では数値目標だけでなく、その戦略の背景や企業の競争優位性、目標に対する根拠などストーリー全体を読み解くことも求められます。
「海外展開で爆発的成長」など、抽象的な表現が多い場合は要注意。具体的な施策と数値目標があるかを確認しましょう。
内容に矛盾がないか、他のIR資料と照らし合わせてチェックする習慣も持ちたいところです。
同業他社の決算説明資料から、目標の妥当性を推測することもできます。
外部環境の影響を自分で補正する
さらに、企業の資料だけでなく、外部環境の影響も考慮する必要があります。決算説明資料には、企業にとって都合の良い内容が中心になりがちで、マイナス要因はあまり強調されません。そのため、以下のような外部リスクは投資家自身が意識的に補正して分析する必要があります。
- 景気後退:消費や投資が冷え込むことで、売上や利益が落ち込む可能性があります。特に内需関連株や景気敏感業種では影響が大きくなります。
- 金利上昇:金利が上がると借入コストが増し、企業の利益を圧迫します。不動産業や設備投資型ビジネスでは特に注意が必要です。
- 為替変動:輸出企業では円高、輸入企業では円安がそれぞれ利益を削る要因になります。企業が業績予想にどの為替レートを想定しているかも確認しましょう。
- 規制変更:業界に対する法規制や税制改正があれば、それが企業活動に与える影響を予測する必要があります。特に医薬品、金融、通信などの規制業種では影響が大きいです。
- 政治リスク:国内外の選挙や政権交代、地政学リスク(戦争・紛争・制裁)なども企業の業績に大きく影響します。グローバル展開している企業は特に注意が必要です。
- 季節要因:業種によっては期ごとにばらつきがある点に注意します。過去の決算から傾向を読み取ることができます。
これらの外部要因は企業のIR資料には詳しく書かれていない場合が多いため、ニュースや経済指標、政府の発表などを通じて自分で補足する姿勢が必要です。
市場環境の急激な変化、競合状況の変化、技術革新などにより、過去のトレンドが将来も続くとは限らないと考えておきましょう。
財務指標と非財務情報を組み合わせて評価する
次に、企業分析においては、財務情報(定量指標)と非財務情報(定性指標)の両面を組み合わせて評価することが重要です。単に売上や利益だけを追うのではなく、その裏にある企業の実力や将来性も見極めなければなりません。
定量指標
- 売上高・営業利益:企業の収益力の基本。伸び率も合わせてチェックしましょう。
- ROE(自己資本利益率)・ROA(総資産利益率):企業がどれだけ効率よく利益を上げているかを示す指標です。
- 自己資本比率・有利子負債比率:財務の健全性を判断する指標。借金の多い企業は金利上昇に弱くなります。
- キャッシュフロー(営業・投資・財務):黒字でもキャッシュが出ていなければ実態は危うい可能性もあります。
定性指標
- 新製品・サービスの開発状況:成長ドライバーとなる製品やサービスがどの段階にあるかを確認します。特許や技術力、競合との差別化も要チェックです。
- DX(デジタル化)・ESG対応・組織改革:近年は企業価値向上に不可欠な要素です。これらに積極的な企業は将来的に評価されやすくなります。
- 経営陣の信頼性・理念・実行力:ビジョンを掲げるだけでなく、それを実現できるかが重要です。過去の発言と実績の整合性も確認しましょう。
進捗率に注目する
中期計画を掲げていても、進捗が悪い企業は要注意です。四半期ごとの数字を見て、目標達成の可能性を冷静に判断しましょう。
推奨書籍
シリーズ累計40万部突破!決算書は最高にシビれる“謎解き”だ!
Twitterで10万人が熱狂する、クイズ×会話で、数字に隠されたビジネス戦略が見えてくる日本で一番売れた会計の入門書。
財務情報×非財務情報こそがポイント。本書「決算分析の地図 財務3表だけではつかめないビジネスモデルを視る技術」では、企業分析の「醍醐味と楽しさ」を堪能できます。
簿記や会計の知識は一定程度勉強したし、決算書の読み方に関する入門書を読んでみたけど、実物の決算書を前にするとどのように読み進めていけばいいのかが分からない。本書は、そのような悩みを持たれた方に、「実物の決算書を自力で読み解くためのチカラ」を身に付けていただくための教科書です。
まとめ
決算説明資料には企業の成長戦略が書かれており、今後の企業の成長予想ができます。ただし、あくまで企業の見通しであり、そのまま実現するかどうかはわかりません。
株で利益を上げるために、この記事で取り上げた7つの注意点を意識して読み込めば、決算説明資料の実現可能性までも推測することができます。
企業の業績を予想し、将来の株価がどのくらい上昇するか推測し、株で利益を上げましょう。
- 進捗率に注目する
- 会社の「見通し」はあくまで仮説である
- 過去の資料と一貫性があるか?
- 数値だけでなくストーリーを見る
- IR資料の「盛りすぎ」に注意
- 外部環境の影響を自分で補正する
- 財務指標と非財務情報を組み合わせて評価する